序文 ピーター・センゲ
成果主義経営は近頃評判が悪い。「どうせ結果が全てだろ」と嘆く人が多い。上司は「数字を上げろ」と言い、結果を出させようとする。しかし皮肉なことに、企業の多くは十分に業績を上げられず、本来の力を発揮できないことが従業員の不満の種になっている。凡庸なチームの一員になりたいと望む者はいない。
ここに大いなる謎がある。成果は皆にとって重要だ。しかし、成果を主義にするのは賢い方法ではない。少なくとも、現在の企業における成果主義はうまくいっていない。
この現状を見ると、飛行機が発明される前に、色々な機械で空を飛ぼうとしていた人たちの昔の映像を思い出す。翼をバタバタさせたり、巨大な丸い傘のような器具が上下したり、四対の翼があるのに、ちっとも浮遊しなかったりする。さまざまな機械の共通の特徴は、どれも飛べない、ということだった。操縦士がどんなに頑張っても同じだ。どんな工夫も知恵も役に立たない。どんなに立派な人でも、気高い志を持っていても関係ない。何をやっても出来損ないの発明品を空に飛ばすことはできない。構造的に飛行が不可能なのだ。
これは、たいていの企業組織が飛翔できない理由と同じだ。人が本当に望む成果を上げることを、組織の構造が許していないのである。どんなに努力しても、どんなにいい人たちでも、どんなに崇高な目標でも関係ない。構造が整えば達成可能な目標が、構造が整っていないと決して達成できない。そして最悪なことに、構造に問題があると気づいている人がほとんどいない。構造的な限界を明らかにする問いを口にする代わりに、翼をバタバタと速く動かすことに一生懸命なのだ。
作曲家・映画製作者として活躍するロバート・フリッツは、この謎に対して独自の視座、そう、創り出すプロセスという視座を提供している。ロバートは、創り出すプロセスを人類史上最高の発明と呼ぶ。人が創り出したいものを現実に創り出すプロセスのことだ。創り出すプロセスは全ての芸術の根底にある。科学の多くもそうだ。特に科学的理解が発明に向けられたときはそうである。過去、四半世紀にわたってロバートは組織の人たちに創り出すプロセスの原理を伝えてきた。ロバートは言う。「最初はただ創り出す方法を学ぶことを手助けしていただけなんだ。でもだんだん組織そのものが面白くなってきて、組織の構造がどう動いているかに夢中になってきたんだ」
ロバートによると、組織を動かすふたつの支配的な構造があるという。緊張構造が支配していて組織が前進する場合と、葛藤構造が支配していて組織が揺り戻す場合である。本書は全章を通じて、このふたつの構造がどう働いているかを明らかにしている。なぜ前者では「成功が成功を呼ぶ」のに対し、後者ではいつも悪戦苦闘が繰り広げられるのか。そして、組織の中にいる当事者たちが、自分たちの運命を左右する構造にいかに影響を与えることができるのか。
「前門の虎、後門の狼」というように、前後から苦難に挟み撃ちにされるような体験を人々がしているときは、葛藤構造が組織を支配している。組織はイノベーションを求めるが、イノベーションにはリスクと失敗がつきもので、失敗を恐れている。組織は顧客の信頼を勝ち取りたいが、顧客本位にすると顧客のためにならない業務を発見することになる。それによって失業したい者は誰もいない。組織は風通しのよい職場をつくって従業員に本音を語ってほしいが、本音を語ることは誰かを追い詰めることにもなり、ややこしい事態を招く。
大真面目に成果重視を標榜する人たちが、まるで逆方向に向かう組織をつくり上げてしまうのはなぜか。葛藤構造の理論はその謎を解き明かす。権力の維持、上司の機嫌を損ねないようにする、体面を保つ、根回しに奔走するなど、成果追求以外のどうでもいいことが、成果を台無しにするのだ。最近、ある著名な元企業経営者がこう漏らすのを聞いた。「私の知る限り、どんな会社でも経営意識の三分の二以上が、お互いを気まずい思いにさせないことに傾けられている」と。
一方で、緊張構造を持つ組織は対照的だ。企業のビジョンとリアリティの両方を大事にすることの意味を理解している。そういう組織は困難に向き合うことを恐れない。彼らにとって、現実は味方である。真実を語ることは、今ここの現実に根を下ろすことであり、力を失うことではない。そういう組織は、主として創り出す志向(反応的な志向ではなく)を持っている。どんな状況に直面しても、そこから自身の志に向かうものだと心得ているからだ。緊張構造が支配する組織においても葛藤は存在するが、それは今の現実の一部として把握され、将来を創り出す上での一要素でしかない。
創り出すプロセスについてのロバートの視座は、昨今の「もっとクリエイティブな」経営アプローチとは一線を画すものだ。たとえば昨今では、「自己組織化」に大いに関心が集まっている。管理者が管理をやめればシステムが勝手に自己組織化するというものだ。これは管理過剰に陥りやすい従来の経営への自然な反動といえる。しかしこれでは、管理職が自由放任にさえすれば、従業員は勝手にうまく組織化すると言わんばかりだ。問題は、自己組織化した結果はたいてい葛藤構造に陥るということだ。緊張構造には至らない。そして葛藤構造が埋め込まれると、組織は揺り戻しを続ける。ジレンマを語ることすら難しくなり、葛藤構造が常態となり、もはや人々が葛藤を見ても気づかないようにすらなってしまう。「組織とはそういうものさ」と受け入れてしまうのだ。
硬直した階層組織を越えるための成功の鍵は、芸術分野ではるか昔から知られている。それは規律と自己統制である。芸術的才能を持つ者の多くが、必要な規律を身につけられず才能を開花させることなく終わる。規律とは、自然に発生するものではない。規律とは、フォーカスのある努力であり、原理と実践ツールによって導かれる。たいていの組織に規律が欠けていることは、人々が現実に何が起こっているのかを見ようとせずに問題解決に明け暮れていることからわかる。まずは目の前の問題を片付けろ、次の問題はその後だ、というように。他に選択肢などないようにさえ見える。近年では、財務危機、リストラ、過剰労働などの問題状況に、とにかく即座に条件反射することが企業組織における仕事のスタイルになってしまっている。この手の条件反射は、葛藤構造を悪化させるだけだ。冷静に事態を振り返って真剣に語り合う時間を誰も持とうとしないからだ。
このように、ロバートの視座は独創的であり、社会科学の分野で過去に書かれたどんなものとも異なる。ここでも、ロバートの独創性はその芸術的バックグラウンドから来ているのだと私は思う。社会構造を分析する大半の社会科学者たちとは異なり、ロバートの焦点は構造を創り出すことにある。その目的は、創り出した構造によって、人が望む方向に企業が動き出すことだ。私見では、ロバートの志向は大多数の組織人の志向に近い。飛ばない飛行機の分析よりも、飛ぶ飛行機を創ることに最大の関心があるのだ。
私が最初にロバートと仕事をともにするようになって20年以上が経つ。以来、ずっと変わりなくロバートは友人であり、私のメンターであり続けた。複雑なテーマを解き明かし、単純明快な原理で効果的なアクションに導くロバートの手際にはいつも驚かされる。しかし、ロバートの単純明快さはしばしば誤解されやすい。物事を矮小化する単純さではなく、物事を浮かび上がらせる非凡な単純化なのだ。つまらないアイデアを複雑にしてみせる安直なビジネス書やマネジメント手法が流行する昨今、幅広い生の現場体験に裏打ちされた深い洞察を見事なほどシンプルに提示してくれるものは滅多にない。
本書がロバートの業績にふさわしい注目と探究をもたらすことを願っている。ロバートは類い稀なる発明家であり、彼の発明は真に独創的だ。象牙の塔のてっぺんから書かれたような経営書に慣れた私たちにとって、ロバートの著書は、地に足が着いている。組織の中で実際に仕事をしていたプロフェッショナルが、現実の組織と現実の人間が、本当に大切な現実の成果を上げるべく学んできた事例が惜しみなく披露されている。
本書は、構造力学の最終版ではなく、むしろ入り口と言っていい。しかし、多くの組織人にとって、本書は優れた組織を築き上げるための素晴らしい第一歩となるだろう。
ロバート・フリッツ来日イベント2019
9/19 「ロバート・フリッツを囲む会」 (Special Session with Mr. Robert Fritz)
9/20-23 創り出す思考
9/25 Zen and the Path of Least Resistance - Robert Fritz & Issho Fujita
9/27-29 Choices
 Evolving
Evolving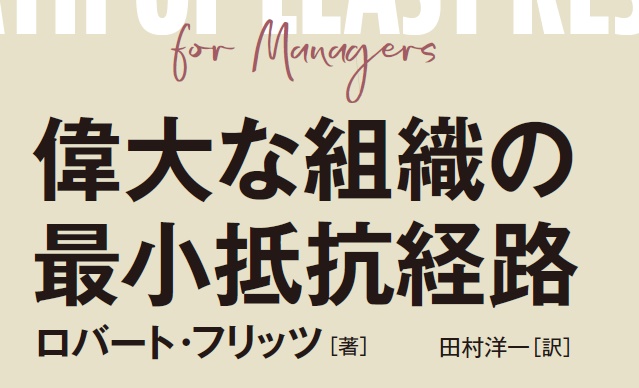



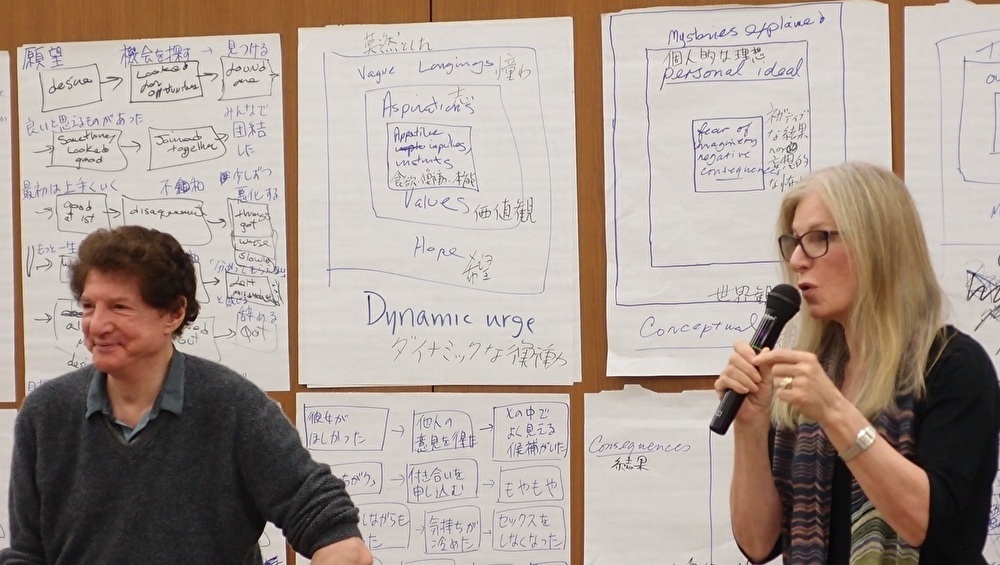


コメントを残す